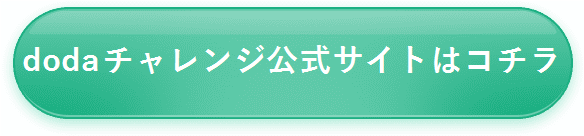dodaチャレンジで断られた!?その理由と対処法を徹底解説

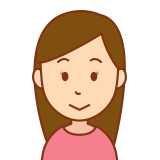
dodaチャレンジに登録したのに「求人紹介ができない」と断られるのはなぜ?
「せっかくdodaチャレンジに登録したのに、求人を紹介できませんと言われた…」そんな経験をした方も少なくないでしょう。ですが、落ち込む必要はありません。断られるにはちゃんと理由があり、それを把握することで今後の対策が見えてきます。
この記事では、dodaチャレンジで断られるケースと、その際に考えられる理由、そして今後どのように転職活動を進めていくべきかを分かりやすく解説します。正しい情報と対策で、転職成功に一歩近づきましょう!
「自分は何が原因で断られたのか分からない」「今後どこに登録すればいいの?」という方も、ぜひ参考にしてくださいね。

dodaチャレンジで断られる理由を知っておけば、対策も立てやすくなります!次のステップに進むためにも、原因をきちんと把握しておきましょう。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、登録者の希望条件とマッチする求人が見つからない場合、「紹介できる求人がありません」と案内されることがあります。特に以下のような条件に該当すると、紹介のハードルが上がってしまう傾向にあります。
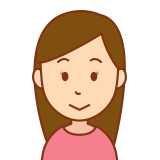
求人が紹介されないのって、自分の条件が厳しすぎるせいかも…?
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
「在宅勤務のみ」や「フルフレックス勤務」「年収500万円以上」などの条件を設定すると、該当する求人が非常に限られます。障がい者雇用枠では柔軟な働き方に限界があることも多く、条件を緩めることで選択肢が増える可能性があります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
アート系やクリエイティブ系のように、専門性の高い職種に絞ると、障がい者雇用枠での募集が非常に少なくなります。柔軟に他の職種にも目を向けると、思わぬ可能性が広がるかもしれません。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方に住んでいる場合、都市部に比べて求人そのものが少ないことが影響します。勤務地を広く考えるだけで、ぐっと紹介される確率が上がることもあるので、一度見直してみるのもオススメです。

希望条件が厳しすぎると、せっかくのチャンスを自分で減らしてしまうかもしれません。少し条件を見直してみると、新しい可能性が見えてくるかも!
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジでは、全ての求職者にサービスを提供しているわけではなく、一定の条件に該当しない場合は、サポートが難しいと判断されることがあります。以下のような場合には、別の支援を案内されるケースもあります。
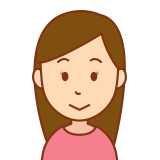
もしかして、私の状態ではdodaチャレンジの対象外なのかも?
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠での求人紹介は、原則手帳が必要)
障がい者雇用枠の求人は、基本的に障がい者手帳を所持している方を対象としています。もし手帳をまだ持っていない場合、取得できるか医師や自治体に相談してみるのもひとつの方法です。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
働いていない期間が長かったり、これまでにあまり仕事をしていない場合、企業側から即戦力として見られにくいことがあります。そのような場合は、職業訓練や短時間勤務の仕事で経験を積むのが現実的なアプローチです。
体調が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
面談で「安定して働くのはまだ難しい」と判断された場合は、dodaチャレンジよりもまず、就労移行支援などを活用して基盤を整えることが優先されます。無理なくステップを踏むことが、長く働くための第一歩です。

サポート対象外と感じたら、焦らず自分に合った準備や支援を受けるのが大切。段階を踏めば、いずれdodaチャレンジを活用できる日も来ます!
断られる理由3・面談での印象や準備不足が影響する場合
面談では、求人のマッチングに向けて求職者の希望や適性を細かく確認します。そのため、準備不足や説明の不十分さが悪印象につながり、求人紹介が難しくなることも。以下のようなケースがよく見られます。
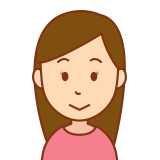
面談で何をどう話せばいいのか不安…。準備不足が原因で断られたりするのかな?
障がい内容や配慮事項が説明できない
自分の障がいの内容や、必要な配慮を説明できないと、適切な職場環境を提供できる企業の紹介が難しくなります。「こういう配慮があれば働けます」という具体例を用意しておくと、面談がスムーズになります。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「何でもいい」では紹介が難しいのが実情。自分が目指す働き方や、やりたい仕事の方向性を言葉にできるよう準備しておきましょう。
職務経歴がうまく伝わらない
過去の仕事をうまく説明できないと、スキルや適性を判断しにくくなります。職務経歴書だけでなく、口頭でも説明できるように整理しておくのがおすすめです。

面談では「自分をどう伝えるか」が大切!しっかり準備して臨めば、紹介の可能性もぐっと高まりますよ。
断られる理由4・地方や完全リモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応ではあるものの、地域や勤務形態によっては求人が極端に少ないケースもあります。特に地方や在宅勤務限定の場合、紹介が難しくなることも。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
都市圏と比べると、地方では障がい者雇用の求人が少ないのが現実です。エリアを広げて探すことで、より多くの求人と出会える可能性があります。
完全在宅勤務のみを希望している場合
完全在宅にこだわると、選べる求人はかなり限られます。多少の通勤も視野に入れることで、紹介される可能性が広がるかもしれません。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジの登録時には、正確な情報が求められます。不備や誤りがあると信頼性が下がり、求人紹介に支障が出る場合があります。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
求人紹介の前提条件となる情報に誤りがあると、紹介された企業とのトラブルの原因になりかねません。正直な情報を記載することが大前提です。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
「まだ働ける状態ではない」と感じながら登録してしまうと、マッチングがうまくいかず、結果として断られてしまいます。タイミングも大切です。
職歴や経歴に偽りがある場合
経歴を偽ることは厳禁。企業との信頼関係が壊れ、dodaチャレンジからの支援も受けにくくなる可能性があります。
断られる理由6・企業側から断られたことを「dodaに断られた」と感じてしまう
紹介は受けたものの、企業の選考で不採用となったケースを「dodaチャレンジに断られた」と感じる人もいます。この場合、doda側の判断ではないことを理解しておきましょう。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業にはそれぞれの採用基準があり、dodaチャレンジが紹介しても不採用になることがあります。落ち込まずに、他の選択肢も検討して前向きに活動を続けることが大切です。

紹介を受けても不採用になるのはよくあること。企業選考に落ちても自分を責めず、前向きに転職活動を続けましょう!
dodaチャレンジで断られた人の体験談まとめ|口コミから見える共通点とは?
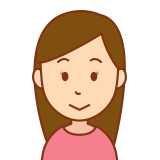
dodaチャレンジに登録しても、なぜ求人を紹介されない人がいるの?リアルな体験談が知りたい!
実際にdodaチャレンジを利用した方の中には、「求人紹介を断られてしまった…」という声もあります。この記事では、dodaチャレンジで求人を紹介されなかった方の体験談を10件紹介し、どんな理由で断られたのかを明らかにしていきます。
「自分も当てはまるかも?」という方は要チェックです。共通点を知ることで、これからの転職活動に役立つヒントが見えてくるかもしれません。
体験談1・障がい者手帳は持っていたけれど、スキルや経験が乏しかった
これまでの職歴が軽作業の派遣だけで、パソコンはタイピングが少しできる程度。資格も特に持っていないため、紹介できる求人がないと言われたそうです。
体験談2・継続して働ける状態と見なされなかった
「まずは就労移行支援などで、安定した就労訓練を受けてください」と案内され、求人紹介には至らなかったとのこと。
体験談3・長期のブランクがネックに
精神疾患で10年以上の療養期間があり、直近の就労経験がなかったことから、「まずは体調の安定と職業訓練を優先しましょう」と言われたようです。
体験談4・地方在住で希望職種が在宅専門だった
四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、ライターやデザインの在宅職を希望したところ、「ご希望に沿う求人はありません」と断られたそうです。
体験談5・正社員経験がなく、アルバイトや短期派遣のみ
dodaチャレンジに登録したものの、「現時点では正社員求人の紹介は難しい」と言われたとのことです。
体験談6・条件が多すぎてマッチする求人が見つからなかった
子育て中で、完全在宅・週3日勤務・時短勤務・事務職・年収300万円以上という条件を提示した結果、「ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです」と言われたそうです。
体験談7・障がい者手帳が未取得だった
うつ病の診断はあるものの手帳は未取得だったため、「障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しいです」と案内されたとのことです。
体験談8・未経験で在宅エンジニア職を希望
長年軽作業をしていたが、在宅でITエンジニアを目指したところ、「未経験からエンジニア職は紹介が難しい」と言われ、求人紹介はされなかったそうです。
体験談9・通勤困難で週5勤務も不可、在宅短時間勤務を希望
身体障がいのため通勤が難しく、短時間の在宅勤務を希望したが、「ご紹介できる求人がありません」と案内されたようです。
体験談10・管理職希望で年収600万円以上を希望
前職は中堅企業の一般職だったが、今回は管理職かつ高年収を希望したところ、「ご紹介可能な求人は現在ありません」と断られたとのことです。

体験談を見てみると、求人が紹介されない理由には「条件の厳しさ」や「サポート対象の外」など共通点があることが分かります。今後の対策にぜひ役立ててください!
dodaチャレンジで断られたときの対処法とは?前向きに次のステップへ進もう
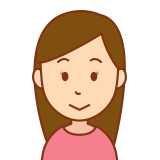
dodaチャレンジに断られたけど、他にできることはあるの?再チャレンジできるの?
「dodaチャレンジで断られてしまった…」という経験をしたとしても、転職活動が終わったわけではありません。なぜ断られたのかを理解し、改善点を明確にすることで、次の一歩へとつなげることが可能です。
例えば、スキルが不足している場合は職業訓練やスキルアップ講座を活用する、ブランクが長いなら短時間勤務や就労移行支援からスタートするなど、状況に合わせた対策を取ることが大切です。
また、dodaチャレンジ以外にもさまざまな就労支援サービスがあります。自分に合った支援を探して、気持ちを切り替えながら前に進んでいきましょう。

断られても諦めないでOK!状況を整理して一歩ずつ対策をすれば、また新しい可能性が見えてきます。
スキルや職歴が理由で断られたときの対処法|一歩ずつ自分をレベルアップ!
「職歴が浅い」「アルバイトや軽作業の経験しかない」「パソコンスキルが心配…」そんな理由でdodaチャレンジに断られてしまうことがあります。でも、それは終わりではありません!スキルや経験は、今からでも十分身につけられます。ここでは現実的な対策を紹介します。
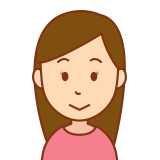
経験やスキルが少ないせいで断られたけど、今から何をすれば良いんだろう?
ハローワークの職業訓練を利用する(PCスキルの習得に最適)
Word・Excel・データ入力などの基本スキルは、事務系求人に欠かせません。ハローワークの職業訓練では、こうしたスキルを無料〜低額で学べる講座が充実しています。就職に直結する内容が多く、実践的に学べるのが魅力です。
就労移行支援を活用する(スキルだけでなく就職支援やメンタル面のフォローも)
就労移行支援では、ビジネススキルやビジネスマナー、面接対策など、働くために必要な力を総合的に学べる場です。体調面に不安がある方でも、無理のないペースでスキルアップが可能です。
資格を取得する(客観的なスキル証明で紹介の幅が広がる)
資格は「自分にはこのスキルがあります」と証明できる強い武器です。Microsoft Office Specialist(MOS)や日商簿記3級は、事務職希望の方に特におすすめ。スキルを可視化することで、紹介できる求人の幅も広がります。

「スキルがないから無理」と思う必要はありません。今からできることを一つずつ始めれば、チャンスは広がります!
ブランクが長すぎてサポート対象外になったときの対処法|少しずつ再スタートを
「長期間仕事から離れていた」「療養していて何年もブランクがある」…そんな状況でdodaチャレンジに登録しても、サポート対象外となってしまうケースがあります。でも、それはもう一度社会に戻るチャンスがないという意味ではありません。小さな一歩から実績を積んでいくことが大切です。
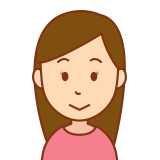
ブランクが長いけど、もう一度働けるようになりたい…何から始めればいい?
就労移行支援を活用して就労訓練を受ける
まずは生活リズムを整えるところからスタート。就労移行支援では毎日の通所を通じて、決まった時間に活動する習慣が身につきます。さらに、企業実習でリアルな業務経験も得られるため、スムーズに次のステップへ進む準備ができます。
短時間のバイトや在宅ワークから始めて実績を作る
週1〜2日の短時間勤務でも、「継続して働けた」という実績はとても重要。いきなりフルタイムではなく、無理のない範囲で働くことが将来的な再就職に大きく役立ちます。
企業実習やトライアル雇用でリアルな経験を積む
企業実習やトライアル雇用を通じて職場の雰囲気や仕事に慣れることで、次回dodaチャレンジに再登録する際の「自信」や「アピールポイント」になります。現場で得た実績は説得力があり、再挑戦の武器になります。

ブランクがあっても、焦らずステップを踏めば大丈夫!実績を積めば、dodaチャレンジでの再登録も現実的になりますよ。
地方在住で求人紹介がなかったときの対処法|視野を広げてチャンスを見つけよう
「通勤圏内に求人が少ない」「フルリモート希望だけど紹介されない」──地方在住の方や在宅希望者にとって、これはよくある悩みです。dodaチャレンジは全国対応ですが、地域によっては求人が極端に少ない場合もあります。そんな時でも、諦めずにできる対策はあります!
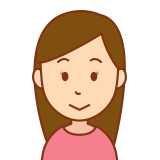
地方に住んでるから求人が少ないのかも…。在宅勤務って他の方法でも探せるの?
在宅勤務に対応した他の障がい者向けエージェントを活用する
「atGP在宅ワーク」「サーナ」「ミラトレ」など、在宅勤務求人に強い障がい者向けエージェントを併用するのがおすすめです。dodaチャレンジと並行して使うことで、より多くの求人に出会えるチャンスが広がります。
クラウドソーシングで在宅実績を積む
「ランサーズ」や「クラウドワークス」といったクラウドソーシングを利用すれば、ライティングやデータ入力のような在宅ワークがすぐに始められます。実績を積んで「働ける証拠」を作ることで、企業の在宅求人にも応募しやすくなります。
地域のハローワークや障がい者就労支援センターに相談する
地元密着型の求人は、転職サイトには載っていないことも。ハローワークや就労支援センターは地域に根差した求人情報を提供しているため、意外なチャンスが眠っていることもあります。通いやすさも考慮されやすいのがメリットです。

地方や在宅勤務希望でも、情報の集め方を変えれば選択肢は広がります!できることから始めて、確実にチャンスを掴みましょう。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたときの対処法|柔軟な考え方で選択肢を広げよう
「完全在宅」「週3勤務」「年収〇万円以上」など、理想の働き方を追求するあまり、条件が多すぎるとdodaチャレンジ側でマッチする求人が見つからず、結果的に紹介を断られてしまうことがあります。そんなときは、自分の希望を整理して柔軟に考えることが大切です。
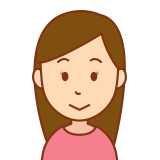
希望が多すぎるって言われた…。全部大事な気がするけど、何か見直せるかな?
条件に優先順位をつける
「絶対に譲れない条件」と「できれば叶えたい条件」を分けて整理してみましょう。例えば「完全在宅が理想」でも、「週1〜2回の出社はOK」にするだけで求人の幅が広がります。優先順位をつけることで、現実的な選択肢を見つけやすくなります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する
条件を見直して再度相談することで、新たな求人を紹介してもらえることがあります。「週5勤務が厳しいけど週4ならOK」「フルリモート希望だけど、月1回の出社は可能」など、現実的なラインを明確にすると、より良いマッチングにつながります。
段階的に理想の働き方を目指す戦略を立てる
今すぐ理想の条件にこだわるのではなく、まずは現実的な条件でスタートし、スキルや経験を積んで理想に近づける戦略も有効です。最初は時短勤務から始めて、慣れてきたらフルタイムや在宅へ移行するなど、ステップアップ形式で働き方を構築するのがおすすめです。

理想の働き方に一歩ずつ近づくために、条件を見直すことはとても大事!柔軟な視点で転職活動を進めていきましょう。
手帳未取得・障がい区分の違いで断られたときの対処法|可能性はまだまだある!
dodaチャレンジは障がい者雇用枠の求人紹介が中心。そのため、障がい者手帳を持っていない場合は紹介が難しくなることがあります。でも、手帳が未取得だからといって、就職の可能性がゼロになるわけではありません。できることから始めて、チャンスを広げましょう。
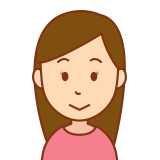
手帳を持っていないと求人は紹介されないの?どうすればいいの?
主治医や自治体に手帳の申請を相談する
精神障がいや発達障がいでも、条件を満たせば手帳は取得可能です。まずは主治医に相談し、自治体で取得の流れを確認しましょう。手帳を取得できれば、障がい者雇用枠の求人への応募が可能になります。
「手帳なしOK」の求人を探す・支援サービスを併用する
ハローワークや一部の就労移行支援機関では、手帳がなくても応募できる求人を紹介してくれることがあります。こうしたルートを使って職務経験を積み、その後に手帳を取得してdodaチャレンジへ再登録する、という流れも有効です。
体調管理や治療を優先し、回復後に再チャレンジ
無理に就職活動を進めず、体調が安定してから再度挑戦するのも賢明な選択です。医師と相談しながら準備を整え、適切なタイミングで再登録することで、より良い条件で就職を目指せます。
その他の対処法|dodaチャレンジ以外のサービスも活用しよう
dodaチャレンジだけが就職支援の全てではありません。断られてしまっても、他の転職エージェントや支援機関を活用すれば道は開けます。
たとえば、以下のようなサービスがあります。
- atGP(在宅対応求人もあり)
- サーナ(老舗の障がい者向け転職サービス)
- ラルゴ高田馬場(発達障がい特化の就労移行支援)
- 地域の障がい者就労支援センター
- ハローワーク(手帳不要求人もあり)
転職活動では、一つの手段に固執せず、複数の選択肢を並行して進めることが成功のカギです。自分の状況に合った支援を見つけ、少しずつでも前に進んでいきましょう。

手帳の有無に関係なく、今できることを進めていけば、必ず次のチャンスが見えてきます。焦らず、自分に合った方法で進んでいきましょう!
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介が難しいのかを解説
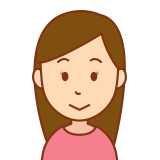
精神障害や発達障害があると、dodaチャレンジでは求人を紹介してもらえないの?
「dodaチャレンジに登録したのに『ご紹介できる求人がありません』と言われた…」という経験をされた方は意外と多く、特に精神障害や発達障害のある方は「自分の障害の特性が原因なのでは?」と不安になることもあるでしょう。
たしかに、障がいの種類や等級、そして希望する条件によっては、マッチする求人が少ないという現実もあります。しかし、「紹介されない=就職できない」ではありません。
この記事では、身体障害者手帳を持つ方と精神・発達障害を持つ方の就職事情の違いに注目しつつ、なぜ求人紹介が難しいケースがあるのか、そしてその対処法について詳しく解説していきます。

精神障害や発達障害でも、働く意欲や準備次第で十分に道は開けます。この記事で可能性を一緒に探っていきましょう!
身体障害者手帳を持つ方の就職事情とは?企業側の受け入れ体制と特徴を解説
身体障害者手帳を所持している方は、精神障害や発達障害のある方に比べて、企業側が配慮しやすいため、比較的スムーズに就職しやすいと言われています。ただし、障がいの内容や等級、業務内容によっては求人が限られることも。ここでは、身体障がい者の就職に関するポイントを詳しく紹介します。
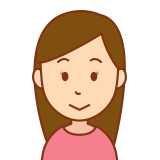
身体障害があると、やっぱり就職しやすいの?どんな配慮があるんだろう?
等級が軽度の場合、就職の幅が広がる
身体障害者手帳の等級が6級や5級など軽度であれば、オフィスワークや軽作業など、多くの求人に応募しやすい傾向があります。企業側も大きな配慮を必要としないため、採用に積極的なケースが目立ちます。
障がいの内容が「見えやすい」から、企業が配慮しやすい
身体障害は視覚的にも判断しやすく、診断書や明確な症状説明も可能です。例えば、車椅子使用者にはバリアフリー、片手に制限があれば片手操作しやすいPC環境を整えるなど、具体的な配慮がしやすく、企業側も安心して採用しやすいのが特徴です。
合理的配慮が取りやすい=採用しやすい
企業が提供すべき「合理的配慮」も、身体障害の場合は比較的明確です。バリアフリーの職場環境、業務内容の調整、補助機器の導入など、企業が準備しやすい支援内容が多いため、採用が前向きに進みやすくなります。
通勤や業務に支障があると求人が限られる
一方で、上肢・下肢に障がいがあり、通勤が困難だったり手作業が必要な業務が難しい場合は、求人が限られる可能性があります。ただし、在宅勤務や事務職など、身体的負担の少ない職種であれば、就職のチャンスは十分あります。
コミュニケーションに問題がなければ一般職への採用も多い
身体障がいがあっても、対人スキルに問題がなければ、事務・営業・カスタマーサポートなど、一般職種にも積極的に採用されるケースが多いです。障がいよりも「どれだけスムーズに社内コミュニケーションが取れるか」が重視される傾向があります。
PC業務・事務職は身体障がい者に人気&求人が多い
身体障がい者の中でも特に人気なのが、データ入力や一般事務などのPC業務。身体的な負担が少なく、長期的に働きやすい職場が多いため、企業側も採用に前向きです。PCスキルがある方は、在宅勤務のチャンスも広がります。

身体障がいがある方でも、配慮しやすい内容であれば企業も積極的に採用してくれる傾向があります。自分の障がいを整理して伝えることがポイントです!
精神障がい・発達障がいの場合は「安定性」と「伝え方」がカギになる
精神障害や発達障害の方が就職活動を行う際に重視されるのは、継続して安定的に働けるかどうかです。企業側は採用後の配慮ができるかを慎重に見極めているため、準備や説明の仕方が重要になってきます。
症状の安定性や継続勤務のしやすさが最重要ポイント
企業側が最も気にするのは「安定して勤務が続けられるか」という点。過去に休職や退職を繰り返していたり、現在も体調が不安定な状態であれば、採用に慎重にならざるを得ません。生活リズムを整え、安定した日常を送れていることをアピールできると印象が良くなります。
見えにくい障がいだからこそ、企業側に不安を与えやすい
精神・発達障害は外見からわかりにくいため、企業側は「突然休職されないか」「対応できるのか」などの不安を感じがちです。だからこそ、「どんな配慮があれば安定して働けるのか」を具体的に伝えることが信頼につながります。
面接時の配慮事項の伝え方が非常に大切
例えば、「月1回の通院が必要」「指示は口頭よりも書面が助かる」といった具体的な内容を伝えると、企業側も対応しやすくなります。ただし、配慮を求めすぎると採用が難しくなることもあるため、最小限のサポートで働けることを示すのもポイントです。
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ方の就職事情|区分で変わる就労の可能性
知的障害のある方が所持する療育手帳は、A判定(重度)とB判定(中軽度)で就職の可能性が大きく異なります。判定に応じて、就労支援の内容や対象となる求人も変わってくるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
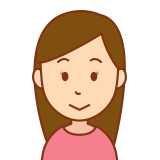
療育手帳のA判定とB判定って、どんな違いがあるの?就職のしやすさも変わるのかな?
療育手帳の区分で就労の選択肢が異なる
療育手帳には重度のA判定と中軽度のB判定があり、A判定の方は福祉的就労が主な選択肢になります。一方、B判定の方は一般企業での障がい者雇用枠に応募できる可能性が高くなります。
A判定(重度)の方は就労継続支援B型など福祉的就労が中心
就労継続支援B型は、一般就労が難しい方向けの福祉的な就労支援で、無理のない範囲で作業を行いながら働く練習ができる場所です。収入は少ないですが、社会復帰に向けた第一歩として非常に重要です。
B判定(中軽度)の方は一般就労も視野に入りやすい
B判定の方は、障がい者雇用枠での軽作業や事務補助などに応募できるケースが多くなります。適切な支援があれば、一般雇用の通常枠で働くことも可能です。就労移行支援などを活用し、職業準備性を高めることがポイントになります。

障がいの種類や区分によって、就職のアプローチも変わります。自分に合った支援や環境を見つけることが、長く働くための第一歩になります!
障がいの種類と就職の難易度|特徴を理解して、自分に合った就職戦略を
障がい者雇用枠の求人では、障がいの種類によって就職のしやすさが異なるという現実があります。これは企業側が求職者に対して「どれだけ配慮できるか」「業務が成り立つか」を重視しているためです。
「配慮がしやすい」「企業が状況を理解しやすい」障がいほど、採用のハードルが低くなる傾向があるのは確かです。たとえば、身体障がい(特に軽度)の場合は必要な配慮が明確で、対応がしやすい分、企業からの求人が多くなります。
一方、精神障害や発達障害は、「見えにくい障がい」であるため、症状の安定性や配慮の伝え方が鍵となり、採用までに少し時間がかかる場合があります。知的障害も、A判定(重度)では福祉的就労が中心となりますが、B判定(中軽度)であれば一般就労の可能性も広がります。
大切なのは、それぞれの障がい特性に応じた戦略と支援を活用すること。dodaチャレンジで断られたとしても、それは「終わり」ではなく「他の方法を探すきっかけ」です。他の支援サービスや福祉機関を組み合わせ、自分に合った仕事を見つけましょう。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |

障がいの種類ごとの特徴を知って、自分に合った道を探していくことが就職成功のカギになります!
障がい者雇用枠と一般雇用枠の違いとは?自分に合った働き方を選ぶために
障がいのある方が就職を目指す際、「障がい者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するかを選ぶことになります。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。どちらが良い・悪いというより、自分の特性に合っているかどうかがポイントです。
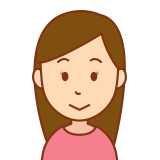
障がい者雇用枠と一般雇用枠、どっちが自分に向いてるんだろう…?
障がい者雇用枠の特徴1:法律に基づいた雇用枠で配慮が前提
障がい者雇用枠は、企業が法律の規定に基づいて設置しているものです。障がいのある方が働きやすいように、職場環境の整備や業務配慮などが前提とされています。
特徴2:障害者雇用促進法により企業には雇用義務がある(2.5%以上)
2024年4月から、民間企業には従業員の2.5%以上を障がい者として雇用する義務があります。この制度により、多くの企業が障がい者雇用を進めており、対象者にとってチャンスが広がっています。
特徴3:障がいを開示し、配慮事項を共有した上で働く
「週に1回の通院が必要」「静かな場所で作業したい」などの配慮が必要な場合は、事前に企業に伝えることで、働きやすい環境が整いやすくなります。
一般雇用枠の特徴1:すべての応募者が同一条件で選考を受ける
一般雇用枠では、障がいの有無にかかわらず、スキルや経験、人物評価で採用が判断されます。障がいによる特別な配慮は基本的に期待できない前提での選考になります。
特徴2:障がいの開示は本人の自由(オープン or クローズ)
一般雇用枠では、障がいを開示する「オープン就労」もあれば、開示せずに働く「クローズ就労」もあります。開示するかどうかは本人の判断に任されています。
特徴3:配慮は原則期待できず、自己対応が前提
一般雇用枠では、通院や勤務時間調整などの配慮は原則行われません。そのため、自分の特性に合った職場選びがとても重要になります。

それぞれの雇用枠のメリット・デメリットを理解して、自分にとって最適な選択をすることが大切です。無理せず、自分に合った道を見つけましょう!
年代別に見る障がい者雇用の傾向|年齢で採用のしやすさは変わる?
障がい者の就職活動において、年齢によって採用の難易度が変わることがあります。特に若年層(20代〜30代)は企業からの期待も高く、比較的スムーズに採用されやすい傾向にあります。一方、40代以降になると、求人の選択肢が減少し、難易度が高くなることも。
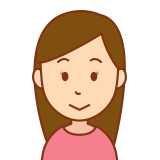
年齢が上がるとやっぱり就職は難しくなるの?自分の年代では何を意識すればいいの?
厚生労働省「障害者雇用状況報告(2023年)」から読み解く
2023年の障害者雇用状況によると、民間企業の障害者雇用率は約2.3%。今後、法定雇用率が2024年4月から2.5%に引き上げられるため、障がい者の雇用機会はさらに広がると予想されています。
若年層(20〜30代)は就職しやすい傾向にある
20代〜30代は「未経験OK」の求人が多く、企業側も教育や育成の余地があるとして採用に前向きです。特に就労経験が浅い場合でも、ポテンシャルや意欲が評価されるケースが多くなります。
40代以降は経験やスキルが重視される傾向に
年齢が上がるにつれ、企業は即戦力を求める傾向が強くなります。特に40代以上では、過去の職務経験やスキルが合わない場合、未経験での就職が難しくなることもあります。
PCスキルや職業訓練で可能性を広げよう
とはいえ、40代・50代でもスキルを磨けばチャンスはあります。在宅勤務可能な職種や専門性のある職種では、年齢に関係なく採用される例も増えています。職業訓練や資格取得を活用し、強みをアピールしましょう。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
|---|---|---|
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |

年齢に関係なく、自分の強みを活かせる方法を見つけることが就職成功の鍵です。年代ごとの傾向を知り、今できる準備を進めましょう!
dodaチャレンジに年齢制限はある?50代・60代でも使えるの?
障がい者向けの就活エージェントを利用する際、「年齢で制限されるのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。実際のところ、dodaチャレンジをはじめとした多くのエージェントでは公式な年齢制限は設けられていません。
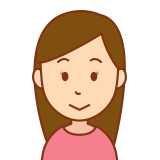
50代や60代でもdodaチャレンジは使えるの?年齢がネックにならないか心配…
公式には年齢制限はないが、実質的には「50代前半まで」が中心
dodaチャレンジには年齢制限が明記されていませんが、実際に紹介される求人の多くは50代前半までの方を対象としているケースが多いのが現状です。企業側が「長く働ける人材」を求める傾向があるため、どうしても若年層〜中年層がメインとなりがちです。
ただし、50代・60代の方でも経験を活かせる仕事や、短時間勤務、専門スキルが活かせる職種などは一定数あります。他の支援機関と併用しながら求人を探すのが効果的です。
ハローワークや障がい者職業センターの併用がおすすめ
年齢がネックになる場合は、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の利用も検討しましょう。これらの機関では、年齢を問わず求人紹介や職業訓練、職場実習などの支援が受けられます。
特に、職歴にブランクがある方や、未経験の仕事にチャレンジしたい方にとっては、こうした機関が心強いサポートとなります。
dodaチャレンジだけにこだわらず、複数の支援サービスを使い分けることで、より自分に合った就職先に出会えるチャンスが広がります。

年齢が高くても、経験やスキル、意欲を活かせる職場はあります。公的支援機関をうまく活用して、転職の可能性を広げましょう!
dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問
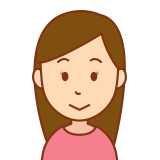
dodaチャレンジを利用する前に、実際の評判やよくある疑問を知っておきたいな。
dodaチャレンジを検討している方の多くが、「実際に使った人の口コミは?」「サポートの質はどう?」といった不安や疑問を持っています。初めて利用するサービスであれば、他の人の体験談や評価はとても気になるポイントですよね。
この記事では、dodaチャレンジに関する「よくある質問」についてわかりやすく解説しています。登録前の不安を解消し、安心して利用するための参考にしてください。
また、各項目には詳しく解説している関連ページも紹介しています。気になる項目があれば、あわせてチェックしてみてくださいね。

質問の前に不安を整理しておくと、dodaチャレンジの活用がグッとしやすくなりますよ!
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの利用者からは、「求人の紹介がスムーズだった」「カウンセリングが丁寧だった」といった良い口コミがある一方で、「希望する求人がなかった」「面談後に連絡が来なかった」といった意見もあります。
実際の口コミや評判について詳しく知りたい方は、以下の関連ページを参考にしてください。
関連ページ:dodaチャレンジの障害者雇用はどう?特徴やメリット・デメリット、口コミを紹介!
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と言われたり、登録を断られたりすることもあります。しかし、原因を理解し適切な対策をとることで、再びチャンスを得ることは可能です。
例えば、スキル不足が理由なら職業訓練を受けたり、他の障がい者向け転職エージェントを併用するのも方法の一つです。詳しい対処法は、以下の関連ページで解説しています。
関連ページ:dodaチャレンジはハードルが高い?断られた理由や対処法、実際の体験談を紹介
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジの面談を受けた後、「連絡が来ない…」と不安に感じる方もいるかもしれません。
面談後に連絡がない理由として、求職者の希望条件とマッチする求人が見つからない、企業との調整に時間がかかっている、または連絡の行き違いなどが考えられます。
具体的なケースや対処法については、以下の関連ページで詳しく紹介しています。
関連ページ:odaチャレンジの連絡なしはなぜ?面談・求人・内定の状況別に理由と対処法を解説!
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、職務経験や希望条件、障がいの特性、必要な配慮などについて詳しくヒアリングされます。
事前に準備しておくと、スムーズに対応できるため、面談の流れや聞かれることを事前に確認しておくと安心です。
詳しくは、以下の関連ページで解説しています。
関連ページ:dodaチャレンジ面談、内定獲得への道筋!流れと対策、事前に知っておきたい注意点と準備
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者の転職支援に特化したエージェントサービスです。
登録すると、専任のキャリアアドバイザーが付き、求職者の希望や適性に合った求人を紹介してくれるのが特徴です。企業とのマッチングや選考対策、面接の調整などのサポートも受けられるため、転職活動を効率的に進めることができます。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジの求人は、基本的に「障がい者雇用枠」が対象となるため、障がい者手帳を持っていない場合は紹介が難しくなることがあります。
ただし、手帳の取得を検討している場合は、アドバイザーに相談することで、手続きに関するアドバイスを受けられることもあります。
関連ページ:dodaチャレンジは障害者手帳が必須?手帳なし・申請中の利用可否を詳しく紹介
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類に関係なく登録が可能ですが、支援の対象外となる場合があります。
例えば、長期間のブランクがあり職歴がほとんどない場合や、体調が不安定で継続勤務が難しい場合は、就労移行支援を勧められることもあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、担当のキャリアアドバイザーに連絡するか、公式サイトの問い合わせフォームから手続きを行うことができます。
退会の際は、今後の転職活動に影響がないよう、事前に確認しておくと良いでしょう。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンライン(電話・Web面談)で実施されることが一般的です。
また、対面での相談を希望する場合は、拠点があるエリアでの面談が可能なこともあるため、事前に確認すると良いでしょう。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには公式な年齢制限はありませんが、実際には50代前半までがメインの対象となっています。
50代後半以降の求職者は、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターを併用することで、より多くの求人情報を得ることができます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中でもdodaチャレンジに登録し、転職活動を進めることができます。
ただし、直近の職歴がない場合やブランクが長い場合は、紹介される求人が限られることがあります。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは基本的に「転職エージェント」のため、新卒向けの求人は少なく、学生の利用は難しい場合があります。
就職活動を進める際は、大学のキャリアセンターや新卒向けの障がい者就職支援サービスを併用すると良いでしょう。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
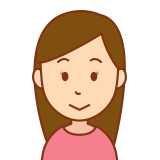
dodaチャレンジって、本当に求人を紹介してもらえるの?他のサービスとどう違うのかな?
dodaチャレンジを利用しようと考えている方の中には、「ちゃんと求人を紹介してもらえるのか不安」「他の障がい者向け就職サービスと何が違うの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、dodaチャレンジでは求職者の条件や状況によっては「紹介できる求人がない」と断られるケースもあります。ですが、これはdodaチャレンジに限らず、他の障がい者就職支援サービスでも起こりうることです。
この記事では、dodaチャレンジの特徴や支援体制について説明しながら、他の代表的な障がい者向け就職サービスと比較し、どのような違いがあるのかを詳しく解説していきます。自分に合ったサービスを選ぶための参考にしてみてください。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
|---|---|---|---|
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー (atGP) |
1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビ パートナーズ紹介 |
350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援 ミラトレ |
非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッド チャレンジ |
260 | 東京、神奈川、 千葉、埼玉、大阪 |
全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、 東海、福岡 |
全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ
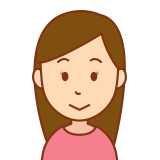
結局、dodaチャレンジで断られるのってどうして?その後はどうすればいいの?
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職支援サービスとして多くの方が利用していますが、中には「紹介できる求人がありません」と断られてしまうケースもあります。その理由は一つではなく、「希望条件が厳しすぎる」「職歴が浅い」「体調が不安定」「地方で求人が少ない」など様々です。しかし、これらの理由を理解し、対策を講じることで再挑戦のチャンスを掴むことができます。
実際にdodaチャレンジで断られた方の体験談を見ると、自身の条件を見直したり、他のサービスを併用したり、dodaチャレンジの障害者雇用はどう?特徴やメリット・デメリット、口コミを紹介!を実践することで再び就職活動に成功している方も多くいます。また、年齢や障がいの種類によって就職の難易度は変わるため、自分の状況に合った支援機関や求人を探すことが重要です。
dodaチャレンジに断られたからといって、就職の可能性がゼロになるわけではありません。必要な準備や行動を重ねていけば、自分に合った働き方を実現する道は必ず見つかります。焦らず、自分のペースでステップアップしていきましょう。

dodaチャレンジに断られても、あきらめる必要はありません。視野を広げて、自分に合った働き方を見つけていきましょう!